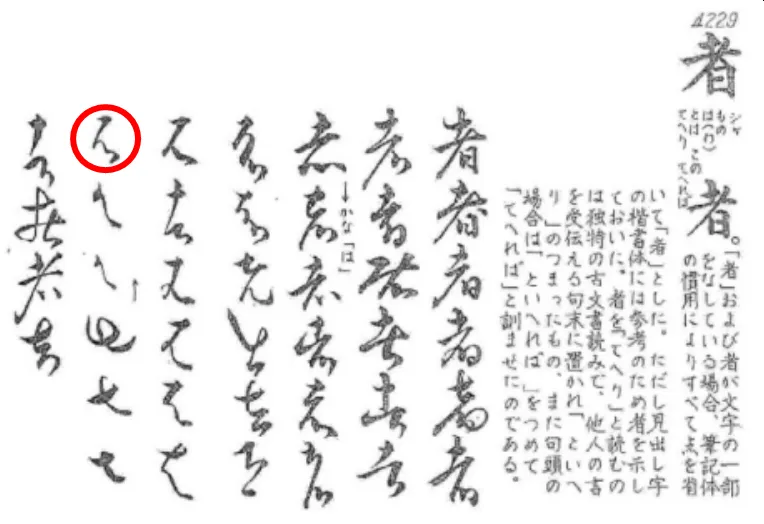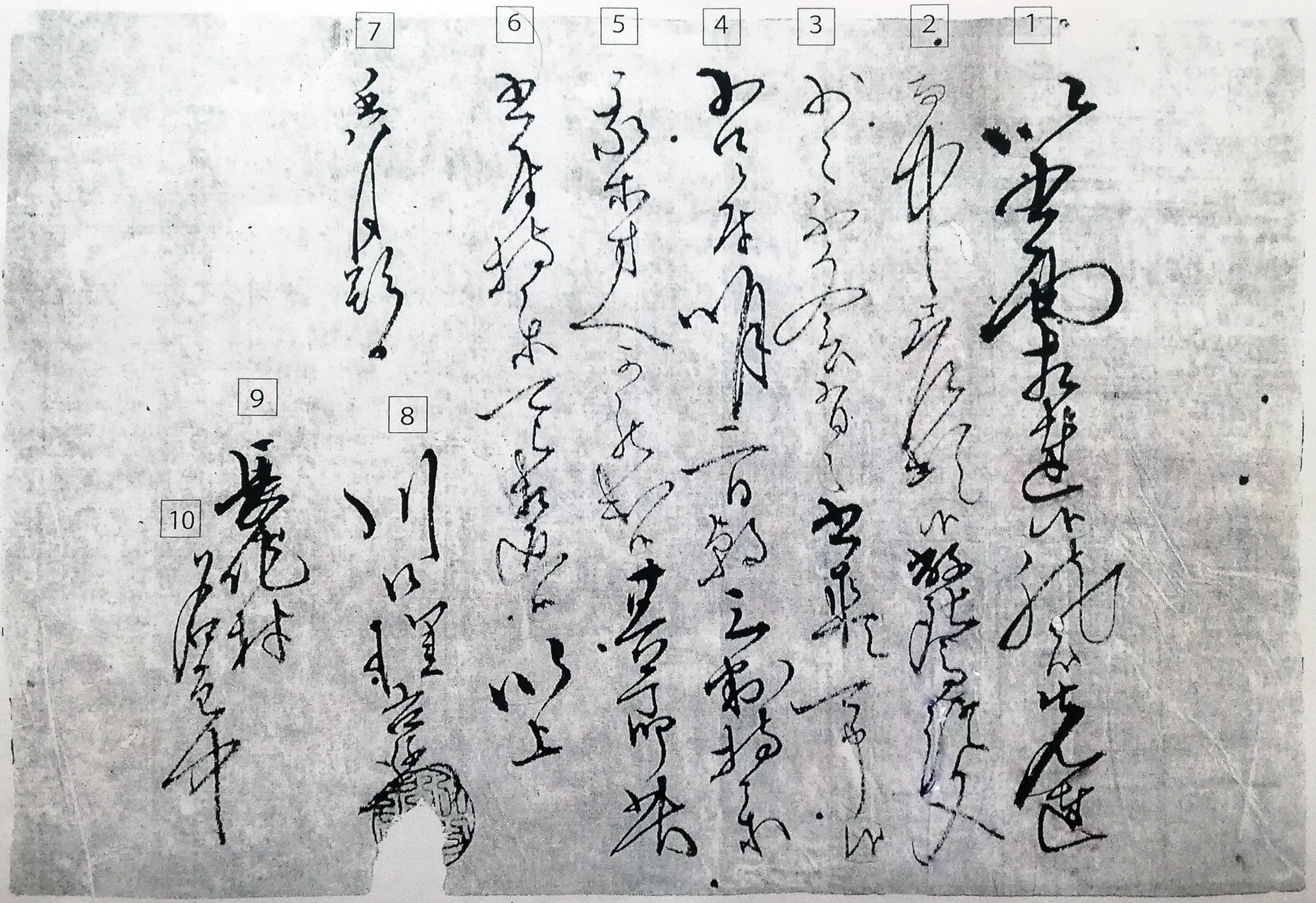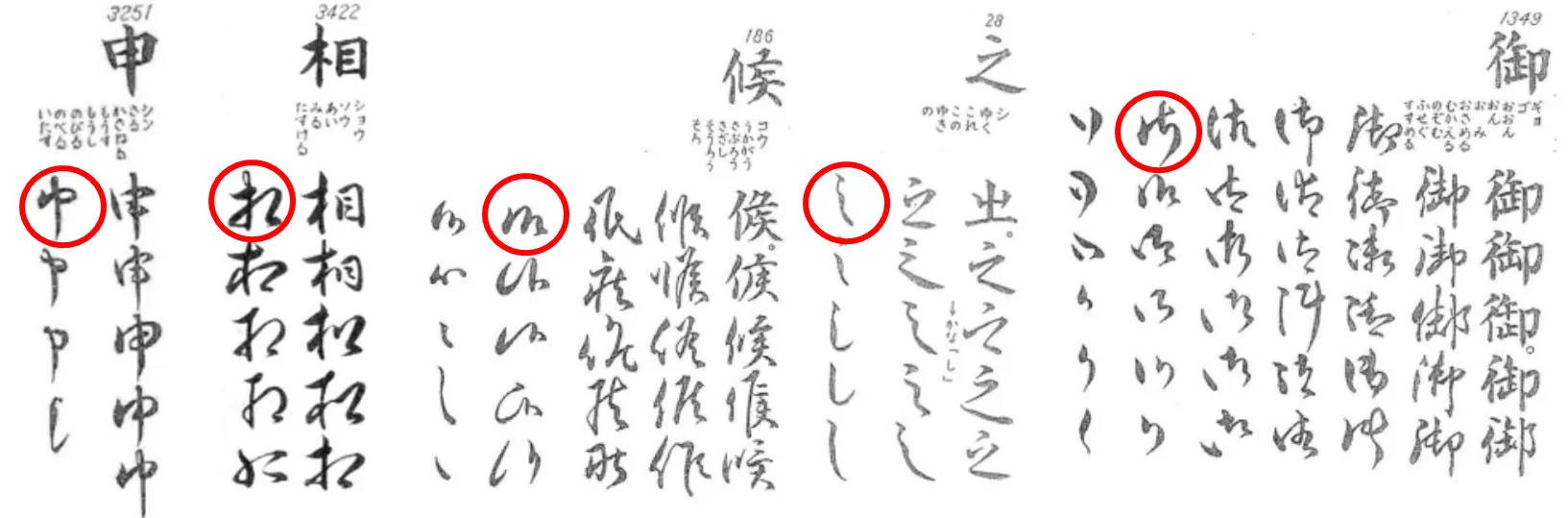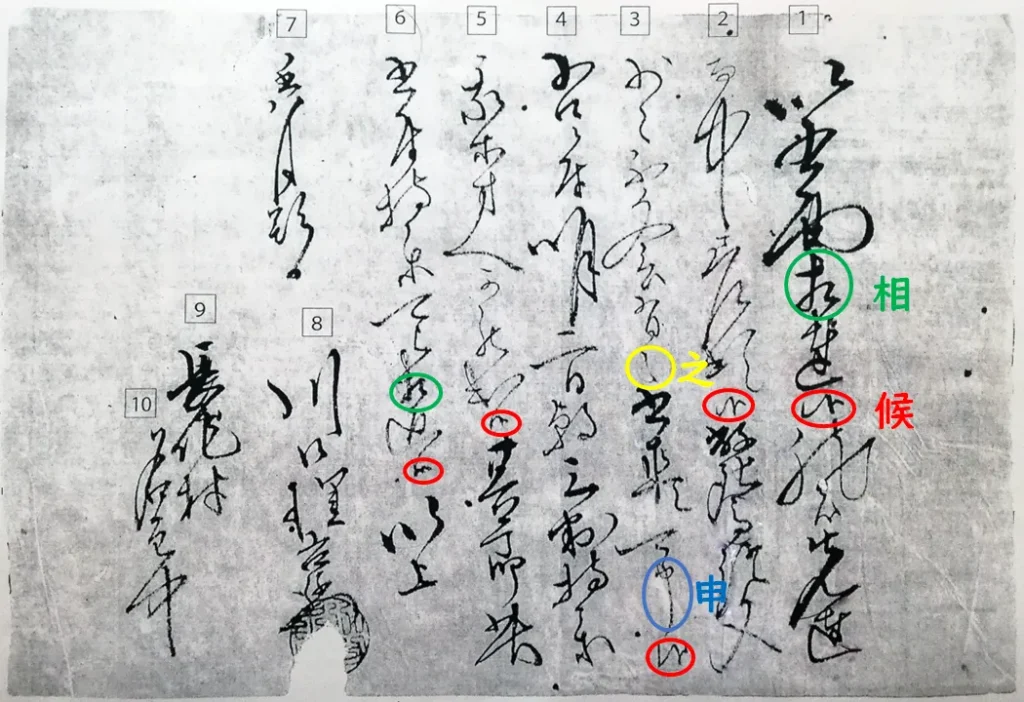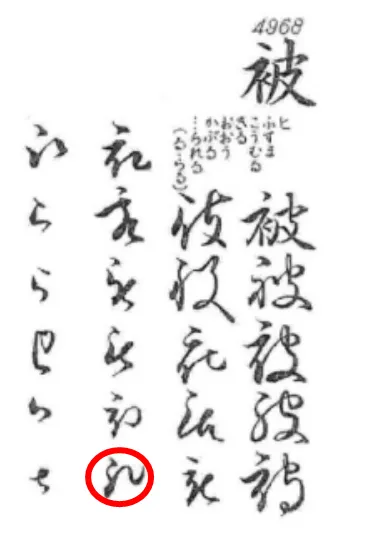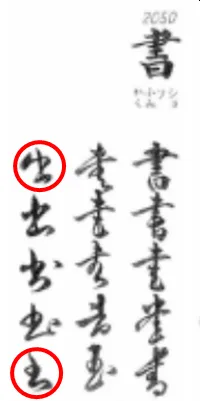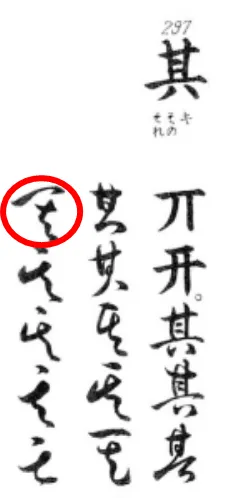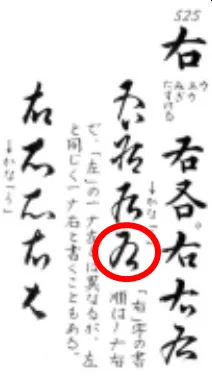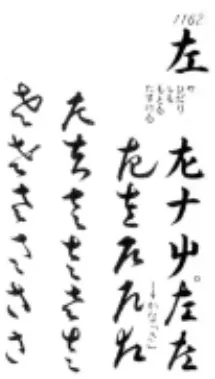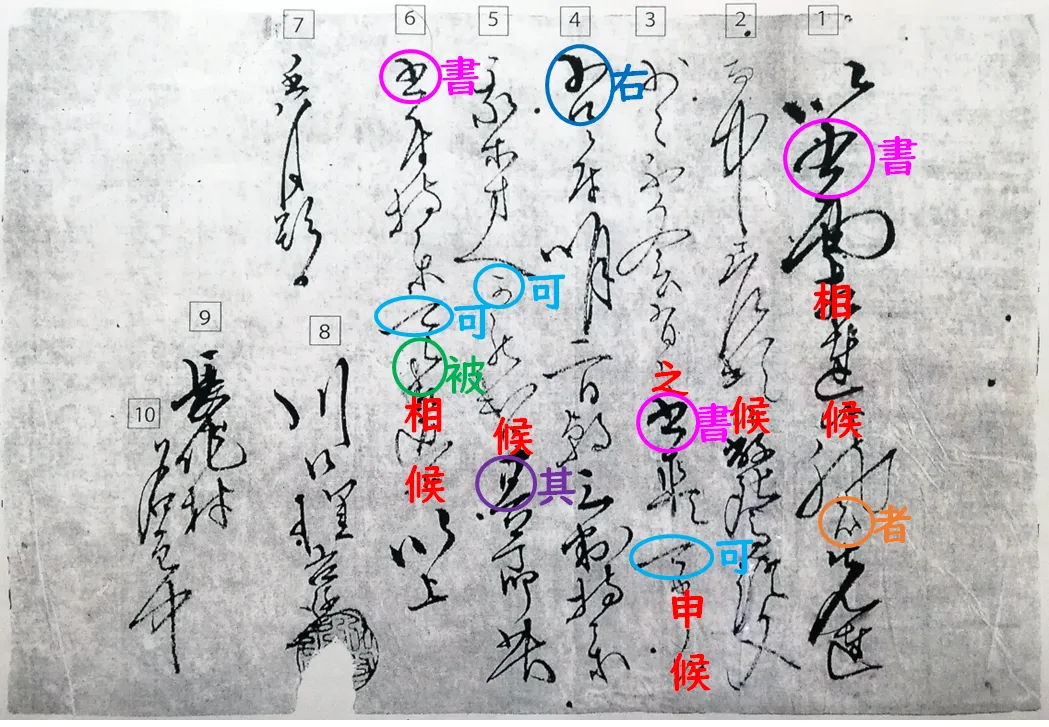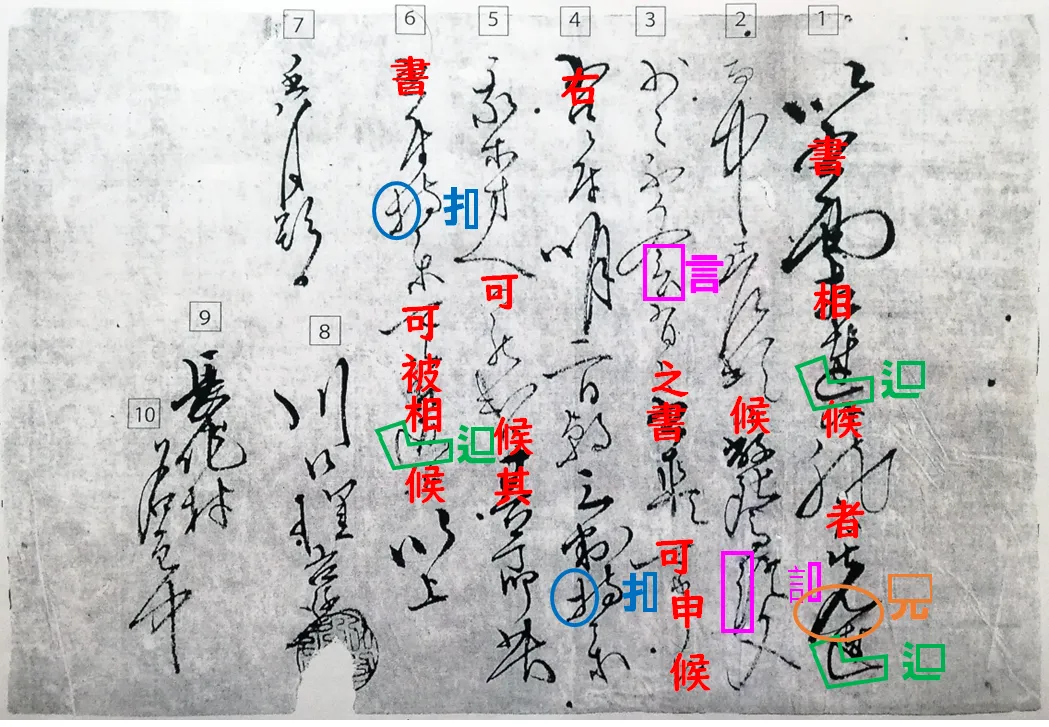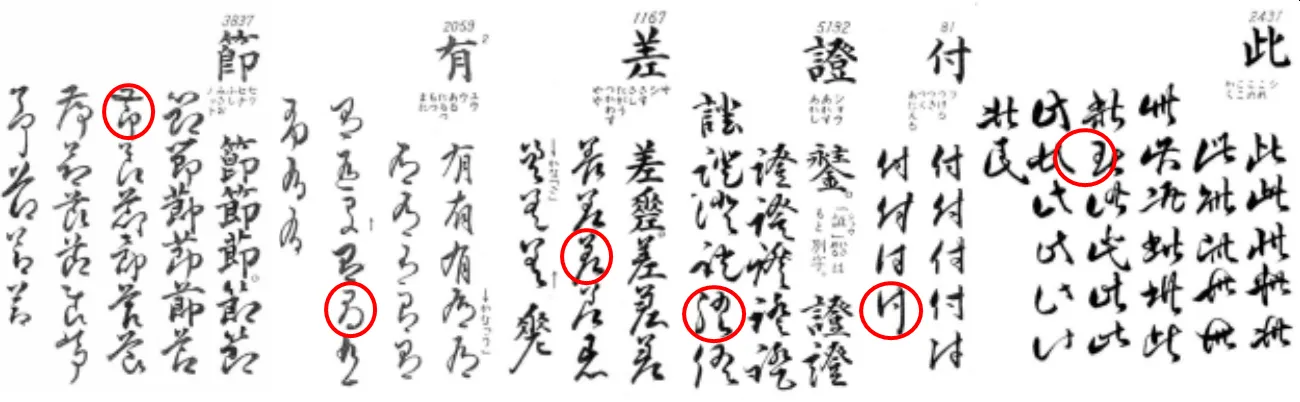現在、日本で「くずし字」を読みこなせる人の数は
人口の0.01%程度(数千人程度)
こんなもの毎日読まないと頭から忘れる、英語と一緒。
独学はシンドいので、3年間申し込みをしてようやく抽選で受講資格を得た。
このたびは、初級古文書講座にお申し込みいただき、ありがとうございました。
厳正なる抽選の結果、受講が決定しましたので、お知らせいたします。
参加者はシニアの方が多い……と思ってたけど、大学生女性も1割、主婦や社会人男性も3割程度いた。
講座内容は
- くずし字辞典とにらめっこしながら進める
- 変体かなを学んでおしまい
かと思いきや、想像以上に説明速度は早く、真面目に理解するには復習が必要なレベルだった。
講座は全部で6回ある。
6回真面目に学べば5割程度は読めるようになることを目標とする……らしい。確かに正しかった。
初級古文書講座「第一回目」内容
くずし字は適当に崩している訳ではなく全国共通のルールで崩している。
- ① 絶対知っておく文字5つを探す
- ② くずしが激しい文字も覚えて探してみる
- ③ 部首を覚えておく
- ④ 文面で頻出語を覚えておく
- ⑤ 文脈から予測する
① 絶対知っておく文字5つ(これだけで最大20%読める文もある)
まず文から次の文字を探す。
- 【候】そうろう(です・ます)
- 【御】おご・おん
- 【之】の・これ
- 【申】もうす
- 【相】あい・そう
埋めた結果が次の通り。
② くずしが激しい文字も覚えて探してみる
※ よく似た崩し字:「左」と「右」、「其」と「者」
※ くずしの激しい文字:門ガマエ、人名(喜兵衛、右衛門など)
これを見つけるのは至難の業。「可」と「書」ぐらいは覚えておこう。
③ 部首を覚えておく
| 訁 | ギリシャ語のゼータ「ζ」 |
| 辶 | 「|_」(角ばった場合と丸みがある場合がある) |
| 扌 | ほぼそのまま「扌」 |
| 先、見、兄 | 下が「ん」 |
部首が分かれば残りの画数で近いものを探す。「る」のように丸みがあれば「持」、「辶」で画数が少なければ「返」など。
④ その他
例えば「参」が「ホ」、「不」が「ふ」、「以」が「い」、「而」が「る」に見える。
また、御触書や証文によく出てくる言葉を覚える。
「罷」「付」「證」「差」「有」「面」「節」「此」「判」
など。
「瓜連・歴史を学ぶ会」の第1,4、6回古文書教室ノートが分かりやすい。

おわりに
AI使って読めたら良いやと思ってたけど、AIでは全く読めなかった。
ただ覚えても普段使いしないので数ヶ月したらすぐに忘れそうだ。
そして、文書によってくずしの形もバラバラなので覚えるのは厳しい。
講師「分からない言葉があれば一日中辞書を見ながら考察する。これが楽しい」
……全く楽しくない。
僕は読めるようになることが目的ではなく、書かれている事を知りたいだけだ。
ほどほどに最低限覚える事にしよう。