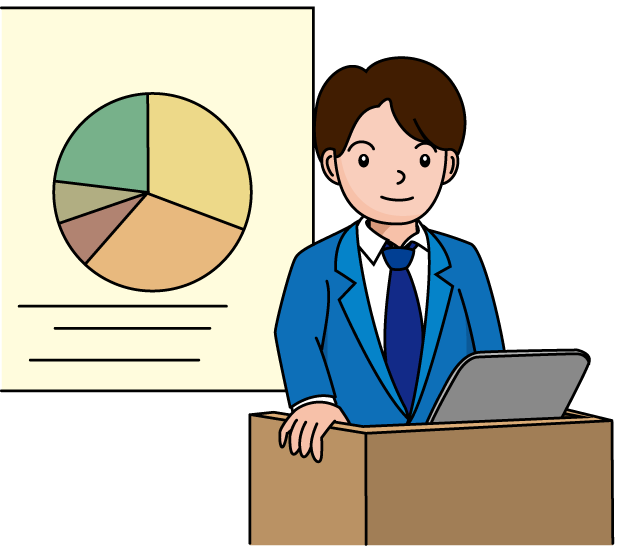学園祭の季節です。
公開研究会などもあるので色々と見て回っているが、、
・・・いや、それって「研究」じゃないでしょ。
という内容が沢山ある・・・。
特に教育過程の研究発表は酷いものだった。論理も根拠もなし。
が、、、そもそも「研究」って何だろう?
もしかして、私の定義が違うのかな・・・。
と思ったので、調べてみました。
「研究」とは何か?
まずは辞書で調べてみる
「研究」を辞書で調べると、次のように説明されていた。
- よく調べ考えて真理をきわめること(広辞苑第五版)
- 物事を深くよくしらべ考えること。物事の事実を明らかにし真理を知ること(旺文社国語辞典)
- 深く調べ考えること(常用国語辞典)
なるほど、なるほど・・・・
・・・いや、それって単なる「調査」じゃね?
「深く調べ考えること(常用国語辞典)」なんて研究と呼んじゃダメだろ・・・。
「調査」と「研究」の違いは何?
それぞれの辞典の情報をまとめると、「調査」と「研究」は次のようになった。
- 「調査」とは、物事の動向や実態を明らかにするために、調べること。
- 「研究」とは、物事の情報を集めて、それを元に考察し、物事の真理を明らかにすること。
ウィキペディアの「研究」の説明が一番わかりやすい。
ある特定の物事について、人間の知識を集めて考察し、実験、観察、調査などを通して調べて、その物事についての事実を深く追求する一連の過程(ウィキペディア)
要するに「調査」「考察」して「研究」となる。
「調査」は「研究」の一過程に過ぎない。
ちなみに「考察」は,結果を解釈し,そこから知見をひきだすことである。
これが出来ない学生があまりに多いが、「考察」を深く記載すると今回の論点がズレるので、またの機会に。
「実践研究」と「実践報告」の定義
「研究」について理解した上で、ようやく本題に入る。
「研究」には色々な種類がある
「研究」の種類を記載する。
| 実証研究 | 直接的な観察や経験によって知識を得る方法 |
|---|---|
| 理論研究 | おもに既存の理論的な研究を整理し、次のような点を明らかにしていくもの |
| 応用研究 | 既存の理論や研究成果を、別な対象に応用し新たな知見を得ようとするもの |
| 制度研究 | 制度をどのように現実に適応すべきか、あるいは現実に適切な制度のあり方や解釈はいかにあるべきかなどを解明するもの |
この中の「実証研究」がクセモノで、「観察」を主眼としているため、「報告」と区別がつきにくい。
今回「これは研究ではなく報告ではないか」と思った発表は「実証研究」に位置付けられる。
なので、次に「実践研究」とは何かを明確にしてみる。
「実践研究」と「実践報告」の違い
まとめると次のようになった。
| 報告(実践報告) | 子ども等への働きかけとその結果をまとめたもの |
|---|---|
| 研究(実践研究) | 子ども等への働きかけとその結果から、相関関係、因果関係を読み解き、新たな事実や事象(問題点の提起や方法の提案など)が提示されたもの |
インターネット上で調査してみると、両者の議論はしばしば起きているようである。
確かにマウスを使った生体実験ではなく、保育が人と人との関わりあいによって展開される人間現象であり言語化しにくいのは理解できる。
ただし、研究結果が「実践報告」にとどまっていたり、「理論的な背景や根拠」が不明確あるいは「論理的な展開」が不十分なものが多いのも事実である。
まとめ
考察しようと思ったが「保育を高める実践教育の手引き(全国保育士会)」を発見した。
そこに「実践研究」の手順が体系立てて書かれていた。
- 1) 先行研究の調査(すでに明らかになっていることの整理)
- 2) 目的の明確化(なぜ、今その実践研究をするのか)
- 3) 達成方法や手続き決定(目的を達成するためにどのような方法や手続きを用いるのか)
- 4) 実践結果と考察(実践の結果をまとめ、研究目的を再度明確化しながら考察)
- ※ 研究自体が「文献」として、次の研究の発展に資するように考え論理的な構成にすること
要するに、実践研究であろうと研究としての基本体系に従えということだ。
このような手引きがあるにも関わらず、ロジカルでも根拠もない発表をしてるのは、研究を舐めてるか、そもそも研究者としての自覚とスキルが低いと言わざるを得ない。
保育者と研究者を兼ねる人材って、そもそも多くない気がするが・・・。
研究とは、なんらかの事実や事象を、根拠を持って明らかにしていく作業である。
※ 従って、研究を始める際には、「自分はこの研究で何を明らかにしようとしているのか」を明確にして臨む必要がある。
※ 従って、研究を終える際には、「自分はこの研究で何を明らかにしたか」が明確になっていなければならない。
要するに、事象を客観的にとらえ、その中に含まれている意味を公正に、しかも正確に解釈したり、合理的に因果関係、相互関係などを追求したりする努力が払われなければならない。
たとえ学校現場で書かれる「実践報告」でも、このように実践しましたということだけでなく、次の要素がいる。
- 何が問題点として提起されるか
- 効果としてどのようなことが得られたか
要するに、教育活動に潜む課題や事実を見つけ出し、提示していくねらいを持って研究活動を行うことが必要である。